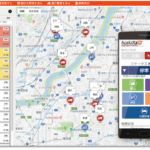前回のコラムでは、休憩時間記録の基本ルールについてお話をいたしました。
ポイントは、休憩した「位置(場所)」「時間帯」「取得回数」です。 これは運送業のこれからの労務管理の超重要ポイントになるのですが、ドライバーに日報に細かく記載してもらうことが前提となります。集計の手間が発生するなど、いろいろと問題が出そうです。ここはデジタコや、装着が不要な車格未満の車両であればスマホアプリを活用するなど、日報の記録を完全デジタル化にもっていかなければ管理がとても大変になります。 やらなければならないことと、時流に合わせたツールの導入、これを絶えず情報を入れ続けなければいけない状況です。
https://app-logi.co.jp/column/?p=7697&preview=true
今回は、燃料、尿素などを含めた給油関連のデジタル化についてです。
デジタル化すべき業務の優先順位

デジタル化を早くすすめなければならない業務の優先順位付けのポイントは、毎日計算しなければならないもので、かつ請求や支払いが発生するものです。 手間も精度も必要になるものですね。 運送業の業務内容を見直してみたときに、給油関連の業務がそれに当てはまります。詳しくは軽油、ガソリン、LNGやCNGを補充したときや、尿素を補充したときの記録です。 運送業の現状の業務方法では、車内機器の導入が進んでいる会社であれば、デジタコに給油量を入力し、その後システム上で集計されます(その機能がないものもあります)。 その時点で燃費も計算され、月間給油量や使用量も掲載され、請求関連の数字もここで計算されます。 デジタル化されているととても業務が楽になることがわかります。 しかしながらタコグラフの装着義務がある車両で、かつランクの高いデジタコを導入している車両であればこのようなことができるのですが、アナログのタコグラフを装着している車両や、装着義務がない車両だとこうはうまくいきません。 ほとんどが給油カードのようなものに給油量と目安の使用量を記入し、月間の集計を事務所に提出するという業務イメージになるのではないでしょうか。 この流れでは全車両の月間の給油量や使用量がわかるまで、翌月までかかってしまいます。 請求数値を計算することだけを目的とするのであればそれでもよいかもしれませんが、日々のマネジメント、燃費管理や原価管理などを行っていこうと思うとそのやり方では難しそうです。 ただ逆にいうとその数値がデジタル化されているのであれば日々のマネジメントも合理的に行えるし、請求関連の業務も合理化されそうです。
全車両の日々の給油管理をなんとか合理的に行えないものでしょうか。
ドライバーが入力するデジタルフォームが必須
経費精算業務の合理化の内容は、乱暴な言い方にはなりますが、経理担当が入力していた伝票類を、営業担当や業務担当が各々入力することです。 つまり入力タイミングを変えることで合理化しています。運送業の場合も同様です。中小運送業では概ね20〜50名(台)のドライバーが稼働していますが、ドライバーがスマートフォンから入力できるような仕組みがあると良いですね。ドライバーが入力→事務員は内容をチェック(桁が大きくずれていないか、前後の日はしっかり入力されているかなど)→集計を確認という流れが理想でしょう。スマホアプリやグーグルスプレッドシートなどを使って、スマホから入力するようなイメージです。 当社で制作しているアプリケーションのイメージはこのような感じです。

これによって給油のデータベースが事務所に自動で出来上がってくると、あとはこのデータから請求書に変換したり、車両別の給油量や使用量の合計を算出したり、燃費のランキング出したりなどなど様々なデータを作成することができます。

これが毎日確認できるようになるのは、デジタル化された業務からの恩恵です。 他にもデジタル化したほうがよい運送業の業務内容は多くあります。随時お伝えしていきます。
こちらでもこの記事を掲載しています。
大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第37回